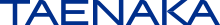3Dプリンターは製造業の救世主?基礎知識から具体的な活用法まで解説
◆はじめに
近年、製造業の現場で「3Dプリンター」という言葉を耳にする機会が増えました。開発スピードの向上やコスト削減に貢献する技術として注目されていますが、具体的にどのようなもので、どんなメリットがあるのか、疑問に思っている方もいるかもしれません。
このコラムでは、3Dプリンターの基礎から、製造業における具体的な活用事例まで分かりやすく解説します。
◆3Dプリンターの基本:モノづくりの常識を変える積層造形
従来の製造方法が、材料を削ったり(切削加工)、型に流し込んだり(鋳造)するのに対し、3Dプリンターはデータを基に材料を一層ずつ積み重ねて立体物を作る「積層造形」という方法を採用しています。この技術により、複雑な形状や内部構造を持つ部品でも、型を使わずに直接製造できるようになりました。
現在主流の3Dプリンターは、主に以下の2種類に大別されます。
【光造形方式(SLA:Stereolithography)】
紫外線硬化樹脂に紫外線を照射して一層ずつ固めていく方式。高精細で滑らかな表面を持つ造形が可能で、複雑なデザインの試作品や、精密な部品の製造に適しています。
【熱溶解積層方式(FDM:Fused Deposition Modeling)】
樹脂を溶かしてノズルから押し出し、積み重ねていく方式。比較的安価なため、試作品や治具の製作によく使われます。
◆3Dプリンターが活躍する業界と適した場面
3Dプリンターは、多岐にわたるBtoB分野でその力を発揮しています。特に活用が進んでいるのは以下の業界です。
【自動車・航空宇宙業界】
軽量化を目的とした複雑な部品の試作・製造。
廃番になった部品のオンデマンド生産。
機能検証のためのプロトタイプ製作。
【医療業界】
患者のデータに基づいた医療モデルの作成(手術シミュレーション用)。
人工関節やインプラントなどのカスタムメイド部品の製造。
医療機器のプロトタイプ製作。
【産業機械・ロボット業界】
治具や工具の迅速な内製化。
多品種少量生産の特殊部品の製造。
デザインや機能の最終確認を行うための試作品製作。
◆3Dプリンターのメリット・デメリット
【メリット】
設計自由度が高い:複雑な形状も一体成形できる
リードタイムが短い:型が不要で、すぐに造形できる
コスト削減:試作段階の費用を抑えられる
【デメリット】
量産には不向き:製造時間が長く、コストがかさむ
使用できる材料が限られる:対応可能な素材が限定的
造形サイズに制限がある:大型部品の製造が難しい
◆3Dプリンターだけでは解決できない課題も
3Dプリンターは試作品や小ロット生産に非常に有効ですが、量産や高い強度、耐久性が求められる部品には向いていません。特に、金属製の複雑な部品を大量に製造するとなると、製造時間やコスト、材料の制限という課題に直面します。
そこで注目されるのが、3Dプリンターと既存の製造技術を組み合わせるハイブリッドなアプローチです。例えば、3Dプリンターでワックス型を製作し、それを使って高精度な金属部品を鋳造する「ロストワックス鋳造」がその代表例です。
ロストワックス鋳造は、高い寸法精度と優れた鋳肌を誇り、多品種少量生産にも対応できます。3Dプリンターでは不可能な、大型部品の一体成形も可能です。
試作段階では3Dプリンターを使い、量産段階ではロストワックス鋳造に切り替えることで、開発スピードとコストを両立させながら、最終製品の品質を最大限に高められます。
3Dプリンターの導入を検討している方も、もし「大型の金属部品を製造したい」「量産を見据えた製造方法を探している」といった課題があれば、ぜひ一度、ロストワックス鋳造も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
ロストワックス鋳造について、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。